〒143-0016 東京都大田区大森北3丁目32-12
休業日 :土曜・日曜・祝日
個人間の金銭消費貸借契約書

親兄弟や親しい友人同士の間でのお金の貸し借りはしないほうがよいですよね。
しかし、場合によっては、お金の貸し借りを行なわざるをえないことがあるかもしれません。そのような時で、金額が多い場合には、金銭消費貸借契約書の作成をおすすめします。
もちろん、金銭消費貸借契約書を作成したとしても、貸したお金が100%返済されるという保証はありません。
しかし、契約書を作成することで、借主に返済への心構えをもってもらうことができます。また、遅延損害金の設定や連帯保証人を立てるなどの方法によって返済をより確実にすることもできます。
ここでは、個人間での金銭消費貸借契約書の意味と作成の際の記載事項、さらに注意点について解説します。
借用書とは
金銭消費貸借契約書と似た書類として借用書があります。効力は同じですが、署名する人が借主のみという特徴があります。
借用書は借主が貸主にお金を借りる際に差し入れる文書とされるので、このような形式となります。
注意すべきは、借用書は貸主が保管するだけなので、紛失や改ざんのおそれがある点です。そのため、金銭の貸し借りについては借用書ではなく、貸主、借主双方が署名捺印する金銭消費貸借契約書の作成をおすすめします。
金銭消費貸借契約書とは

金銭消費貸借契約書とは、金銭貸借について、金額、返済日、返済方法などの条件を定め、貸主、借主双方が署名捺印をして作成する書類です。
金銭消費貸借契約書を作成するメリットは金銭貸借の事実を明確にし、返済方法について定めることで返済を確実なものにできる点にあります。
たとえ口約束でも、金銭の授受が行われたうえであればその効力は有効とされますが、内容が明確でなければ意味がありません。
金銭消費貸借契約書が作成してあれば、金額や返済期限、返済方法などが明確になり、後日起きるおそれのあるトラブルを予防することができるのです。さらに、作成した金銭消費貸借契約書は、双方が1部ずつもつので紛失や改ざんのおそれも低下します。

口約束と金銭消費貸借契約書
金銭の授受を行う前には、口約束(諾性的消費貸借契約と呼びます)では契約は成立しません。民法の改正により、金銭の授受が行われる前には書面等によらなければ契約は成立しない、と定められたからです。(民法第587条の2)
ただし、ここでいう書面とは正式な金銭消費貸借契約書でなくてもかまいません。メールなどによって債権者債務者双方の金銭貸借を行う意思が明確である文書であれば、契約として認められます。
金銭消費貸借契約書の記載事項
個人間での金銭消費貸借契約書に記載する事項は次の通りです。
- 日付(借入日、契約書作成日)
- 貸主
- 借主
- 金額
- 返済方法(一括払い、分割払いのどちらかを選択。分割払いの場合、支払明細表も添付)
- 返済期日
- 連帯保証人 (必ずしも記載する必要はなく、当事者同士の交渉による)
- 利息 (必ずしも記載する必要はなく、当事者同士の交渉による)
- 遅延損害金 (必ずしも記載する必要はなく、当事者同士の交渉による。ただし、記載がなくても効力は発生する)
- 期限の利益喪失条項(必ずしも記載する必要はなく、当事者同士の交渉による)
ここからは、連帯保証人、利息、遅延損害金、期限の利益喪失条項について解説いたします。
連帯保証人

連帯保証人とは、お金を借りた人が返済できない場合に、その人に代わって借りた金額を返済する義務をもつ人のことです。
借主の返済能力に疑問がある場合の人的担保として設定されます。
個人間での金銭消費貸借契約書では連帯保証人を立てるか否かについては、双方の話し合いによります。連帯保証人がいなくても双方が納得していれば問題はありません。
なお、連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益といった債権者に対抗する手段がなく、債権者からいつでも貸金の返済を求められる可能性があり、それを断ることができません。連帯保証人になるのは非常に危険です。
利息

金銭消費貸借契約を結ぶ場合、利息についての定めがなければ、借主は利息を支払う必要はありません。
民法では、契約書のなかに利息を付ける特約がなければ貸主は利息を請求することはできない、とされているからです。(民法第589条)
利息を付ける場合には、その旨を契約書に記載する必要があります。その際には利息の上限に気を付けなければなりません。
利息の上限は金額に応じて次のように決まっています。(利息制限法)
| 金額 | 利息の上限 |
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円~100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
これ以上の利息を定めても、その分は無効となります。貸主がすでに利息制限法に定める利息以上の金員を受け取っていた場合には、その分は元本に充当されることとなります。元本が0円になった後も支払いが続いていた場合、その分は過払い金として借主のほうで返還を求めることができます。
また、出資法では個人間の金銭貸借の利息は年109,5%とされていますが、これについても利息制限法を上回る利息分は無効です。さらに、出資法に定める利息を超えた場合には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられるか、または両方の罰が併科されます。
遅延損害金
遅延損害金とは、借主の返済が遅れた時に発生する損害金のことです。この条項は金銭消費貸借契約書に記載しなければならないわけではありません。
しかし、利息と違い、金銭消費貸借契約書に記載がなくても、借主は貸主から遅延損害金の請求を受けた場合には、支払う必要があります。いわば、金銭消費貸借契約上、当然に発生するものと理解してください。
遅延損害金の利息については、契約書に定めがない場合には民法に規定された法定利息年3%が適用されます。しかし、民法改正に伴い、この法定利息は3年ごとに見直しがされることとなりました。そのため、契約書に利息を定めていない場合には、3年ごとに見直される利息が適用されることとなります。
ただし、適用されるのは実際に遅延による損害が生じた時点での利息です。仮に、遅延損害金を支払っている最中に3年ごとの見直し時期が到来したとしても、損害が生じた時点での利息が変わることはありません。
法定利息が3年ごとに変わる変動制となったことで、遅延損害金の利息も変動します。そのため、遅延損害金の利息を定めない場合には、利息の変動について注意する必要がでてきます。
この点につき、あらかじめ遅延損害金の利息を定めておけば、利息の変動に左右されることはありません。契約時に定めた利息が、3年ごとの見直しに関わりなく適用されるからです。
しかし、契約書に記載する場合には利息制限法が規定する次の利息を超えることはできません。
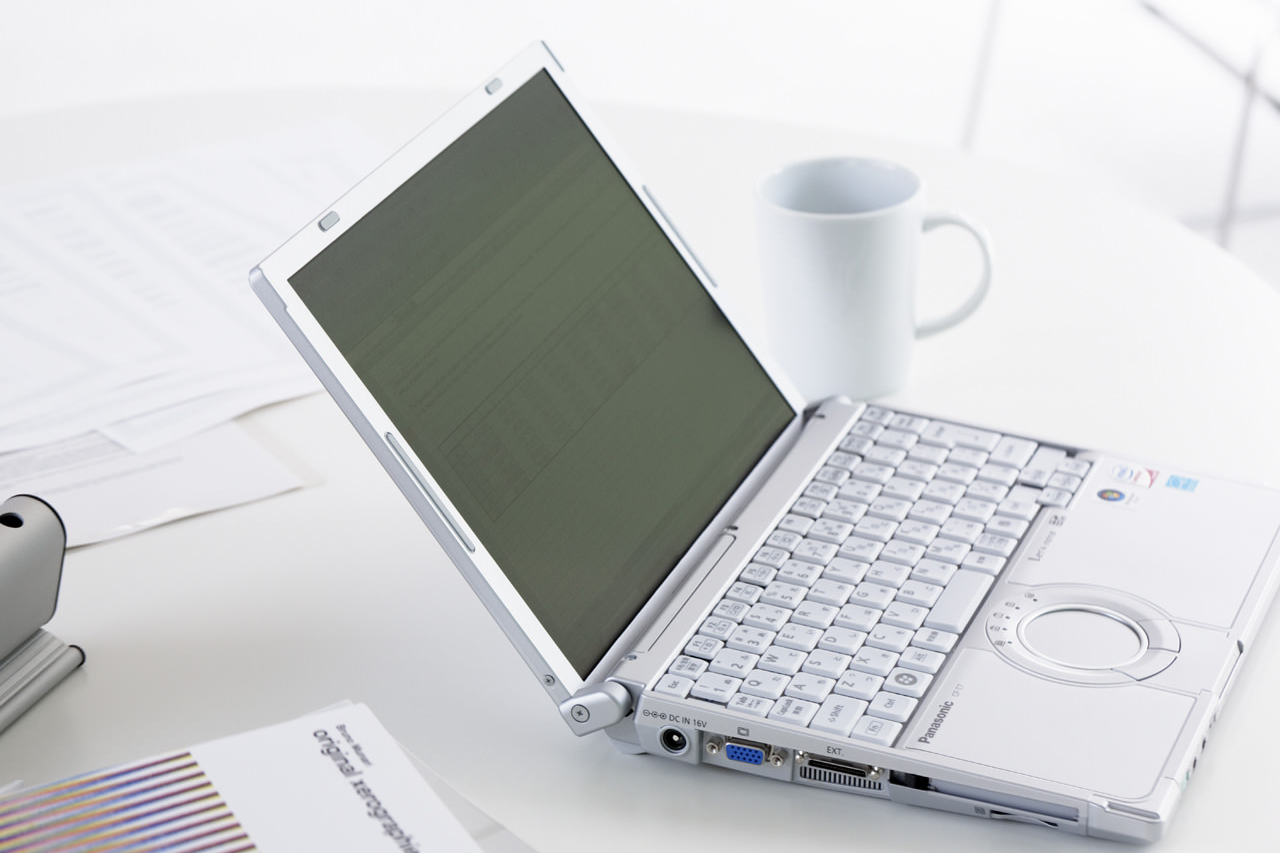
| 金額 | 利息の上限 |
| 10万円未満 | 年29,2% |
| 10万円~100万円未満 | 年26,28% |
| 100万円以上 | 年21,9% |
利息制限法では、個人間の遅延損害金の利息は先述した利息の1,46倍が限度とされているからです。
期限の利益喪失条項

期限の利益喪失条項とは、借主が支払いを怠ったり、破産したりした場合などに、貸主から借主に対して残った債務のすべてを一括して返済するように求めることができる条項をいいます。
借主の側からいえば、期限の利益とは、返済期限が来るまで借主は借りたお金を返さなくてもよいという意味です。
たとえば、返済日が毎月の月末として決まっていれば、毎月の月末までは、お金を返す必要がないのです。
しかし、冒頭で紹介したような理由で返済ができない場合には、期限の利益が喪失し、借主は残金を一括して返済しなければなりません。
期限の利益が喪失するのは主に次の場合です。
- 借主が返済を怠った時(回数は決まっていないので、当事者同士の相談による)
- 借主の競売、破産、民事再生手続きの申し立てがあった時
- 借主に租税の滞納処分があった時
- 借主が貸主に通知しないで住所を移転した時
貸主からすると、返済を担保するために必要な条項ということができます。
注意しなければならないのは、期限の利益喪失条項が契約書に記載されていない場合には、貸主は借主に対して残金の一括請求を行なうことができないことです。
たとえば、50万円を貸していて、毎月5万円ずつ返済するといった契約があるとします。その返済がストップした時には、期限の利益喪失条項が契約書に記載されていなければ、貸主は残金の一括請求はできず、毎月の返済額(5万円)の請求ができるだけとなります。
金銭消費貸借契約の時効

金銭消費貸借契約には時効があります。債権者が金銭の返還を請求できることを知った日から5年間、もしくは10年間のいずれか早い時期に時効となるのです。
貸したお金を返す期限を債権者が知っていれば5年間、忘れていたとしても10年間経てばその金銭消費貸借契約は時効となり無効となる、とご理解下さい。
ただし、黙っていても自然と時効が適用されて金銭貸借契約が無効になるわけではありません。時効によって金銭貸借契約を無効にするためには債務者側が時効になったことを主張する必要があるのです。
この主張を時効の援用といいます。内容証明書によって債権者に通知するのが一般的です。
なお時効の進行をリセットすることができます。債権者が裁判上の強制執行手続きを行なうか、もしくは、債務者のほうで貸金の一部を返済したときなどです。
債務承認弁済契約書について
お金を貸していて、返済を受けている途中であっても、金銭消費貸借契約書を作成することができます。これを債務承認弁済契約書と呼びます。
たとえば、契約書がないため、借主からきちんと返済されるか不安な場合や、すでに金銭消費貸借契約書は作成しているが、内容を変えた契約書を新たに作り直したいといった場合に作成されます。
契約書の文言が変わるだけで、基本的に金銭消費貸借契約書と同じ効力をもつ契約書になります。
印紙税について
金銭消費貸借契約書は印紙税法上の課税文書の一つであり、印紙税が課税されます。具体的には作成した契約書に印紙税額が記載された収入印紙を貼り、消印をすることで納税を行ったとみなされるのです。
課税額は貸し借りをする金銭の額によって異なります。たとえば、100万円を貸した時の課税額は1,000円です。ただし、貸した金額が1万円以下の場合には印紙税の課税対象とはならず、その金額で作成した金銭消費貸借契約書に収入印紙を貼る必要はありません。
収入印紙を貼るのは当事者双方が署名押印した契約書になります。すなわち、署名押印した金銭消費貸借契約書を双方がそれぞれ1通ずつもつのであれば、両方に収入印紙を貼ることが必要です。
その際、印紙代はどちらが負担してもかまいません。双方で折半することもあるようです。
なお、収入印紙を貼らなかった契約書であっても法的には有効となります。しかし、印紙税は税金なので、契約書の有効無効に関係なく納付しなければなりません。もし、納付しなかった場合には納付金額の3倍にあたる過怠税が課せられてしまいます。
公正証書による金銭消費貸借契約書の作成

金銭消費貸借契約書はお金の貸し借りをした個人同士で作成しても有効ですが、公正証書で作成するほうが、債権の担保手段としてはより効果的です。
公正証書は、公証人によって作成されるので間違いがありません。
また、契約書を執行認諾文付公正証書として作成すると、貸金の返済に関して争いが生じた時には、その公正証書を使って、相手の資産に対して、直接強制執行をすることができます。
通常の金銭消費貸借契約書の場合、相手の資産を差し押さえるためには、裁判を行なって勝訴判決を勝ち取り、債務名義を得る必要があります。債務名義とは、相手の資産を強制的に差し押さえることができる権能をもった書類のことです。
執行認諾文付公正証書とは、裁判手続きを経なくとも、債務名義となる書類をいいます。金銭消費貸借契約書を執行認諾文付公正証書として作成すれば、貸金の回収が難しくなった場合でも、裁判手続きを踏まずに相手の資産に対する強制執行ができます。
貸主にとっては、債権の回収が容易になるメリットがあります。
まとめ

親しい友人同士でお金の貸し借りをした場合、返済の時点でトラブルになってしまい、その結果としてそれまでの関係が壊れてしまう、ということが多いようです。
そうならないためには、友人間での金銭貸借をしないことがよいのですが、そうはいかないこともあります。
そのような時には、金銭消費貸借契約書を作成して、互いにルールを守ることが大切でしょう。
当事務所では、個人間での金銭消費貸借契約書の作成をサポートいたします。公正証書として作成する場合には、公証役場との打ち合わせも行ないます。
金銭消費貸借契約書の作成を検討中の皆様、ぜひ、当事務所にご相談ください。
電話やメールでの相談は初回無料です。
オンライン通話のご利用について

当事務所では、面談によるご相談や業務のご依頼を頂いた場合、ご希望に応じてオンライン通話による打ち合わせ等を行っております。(有料)
くわしくは以下のページをご覧ください。
なお、公証役場では対面による手続きが必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
契約書作成メニューは次の通りです。


































